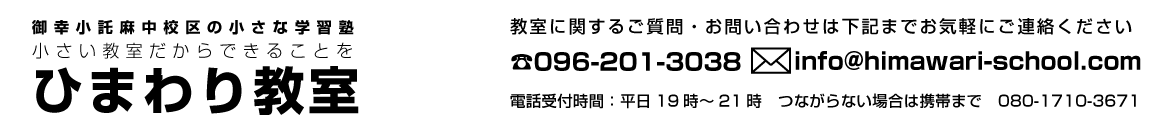しつけの習慣から学ぶ、生徒との接し方と指導の工夫
指導の質を高めるために
日々、生徒と向き合う中で、「もっと良い声かけができないか」「どうすればやる気を引き出せるか」と試行錯誤しています。ただ教えるだけでなく、生徒が自ら学びたくなるような環境を作りたい。そのヒントを得るために、多湖輝著『しつけの習慣』を手に取りました。
この本には、しつけや教育に関する数多くの示唆がありましたが、特に印象に残った2つのポイントを紹介します。
本書を選んだ理由
今回、多湖輝著『しつけの習慣』を読んだ理由は、大きく二つあります。
- 生徒との基本的な接し方やしつけを学び、指導に活かしたいと考えたこと
- 「子どもを伸ばすほめ方・しかり方の知恵」という項目に特に興味を持ったこと
その中でも特に印象に残った2点について、まとめてみます。
1. 励ましやほめ言葉は、毎日繰り返すほど効果がある
「自信のない子」に対して励ましたり、ほめたりする際、その場限りではなく、毎日繰り返すことが重要である。プラスの暗示とは、信じ込ませること、思い込ませることから始まる。そのため、「あなたはやればできる」と単発で伝えるだけでは、効果は期待できない。たまに言われるだけでは信じられず、逆に不信感を抱くこともある。
この内容を読んで、確かにその通りだと実感しました。
これまで私は、「生徒を毎日ほめると慣れてしまい、ありがたみが薄れるのでは?」と考え、適度な頻度でほめることが良いと思っていました。しかし、ほめられて嫌な気分になることはなく、むしろ継続的な働きかけが生徒の自信につながるという視点は、新たな発見でした。
特に成績上位の生徒に対して、「できて当たり前」と思い、ほめる機会を減らしてしまっていたことに気づきました。今後は、どの生徒に対しても意識的に継続的にほめることを心掛けたいと考えています。
2. 「あなたは…」ではなく「私は…」で叱るとうまくいく
本書では、次のような例が紹介されています。
- A 「給食は残さず食べなさい!」
- B 「給食は栄養のバランスを考えて作られているから、あなたの体のためにも、お母さんはちゃんと食べたほうがいいと思うんだけど。」
このように、「あなたは~しなさい」と命令口調で伝えるよりも、「私はこう思う」と伝えることで、子どもは素直に受け入れやすくなるとのこと。
これを指導に応用すると、例えば次のようになります。
- A 「書いて覚えなさい!」 → B 「先生は書いてみたら覚えやすかったよ。」
- A 「静かにしろ!」 → B 「みんなも勉強してるから、集中できるほうが先生はいいと思うんだけど。」
- A 「この勉強法を身につけなさい!」 → B 「先生はこの方法で成績が上がったよ。」
このような言い方に変えることで、生徒が「やらされている」と感じるのではなく、自ら考え、気づき、行動につなげることができるのではないかと感じました。
強制されるのではなく、自分の意思で学ぶことができれば、勉強する意味そのものを考えるきっかけにもなり、将来的には自立した大人へと成長していく可能性が高まります。
もちろん、すべてがうまくいくとは限りませんが、こうした工夫を取り入れることで、より良い指導ができるのではないかと期待しています。
まとめ
本書には、しつけや教育に関する多くの学びが詰まっています。ただ、一度にすべてを吸収しようとすると実践が難しくなるため、今回は特に印象に残った2点に絞って取り上げました。
- ほめ言葉は毎日繰り返すことで効果を発揮する
- 「あなたは…」ではなく「私は…」で伝えることで、より受け入れられやすくなる
これらを実践し、自分の指導スタイルに取り入れることで、生徒との関係をより良いものにしていきたいと考えています。